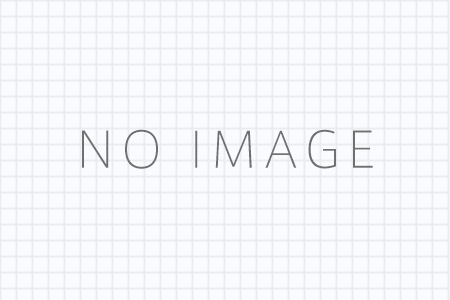生命維持の根幹を見極める脳脊髄液
頭蓋骨と背骨の内部には、人間の全身機能をコントロールする脳と脊髄が存在します。この中枢神経系は繊細なため、三重の髄膜(硬膜・くも膜・軟膜)で包まれて、記憶を脳脊髄液(CSF)が満たしています。脈絡叢で血液を原料として産生され、脳と脊髄のくも膜下腔を循環した後、くも膜顆粒血管に戻ります。この循環システムは、脳の自重による物理的圧迫を回避し、外部からの衝撃を吸収する「液体のクッション」として働いています。
脳脊髄液の役割の詳細
特に睡眠時に脳脊髄液の流れが増加し、脳内のアミロイドβやタウタンパクなど、神経変性疾患(アルツハイマー病など)の原因となる有害物質が集中的に除去されることが最新の研究で明らかになっている。
この一連の流れは、脳室系とくも膜下腔を経て、最終的には静脈やリンパ系を通って全身まで老廃物を排出します。また、脳脊髄液にはグルコースやミネラルなど、神経細胞が機能するために必要な栄養素も含まれています。
脊髄液は脈絡約で定期的に産生・吸収されており、成人で総量140ml~500ml(年齢により変化)とされています。1分間に6~12回のサイクルで生成と吸収が行われ、頭蓋骨や仙骨もごくわずかながら並行して動いています。この律動性が、代謝や神経活動のリズムに影響を与えます。
脊髄液循環障害がまずは不調
脊髄液の流路は狭小で、頭蓋骨や仙骨の歪み、筋膜の緊張などにより流れが慌てられることがあります。流れが滞ると脳圧が上昇し、頭痛やめまい、慢性疲労、場合によっては水頭症など重篤な神経疾患に至る可能性も指摘されています。
さらに、脳脊髄液の循環不良は自律神経系にも悪影響を一時、頭痛、不眠、睡眠、息切れ、しびれ、低体温など多岐にわたる不定愁訴や自律神経失調症を控えます。慢性的な流れの障害は、ホルモンバランスの乱れや耳鳴りなど、脳神経細胞自体の機能障害に対抗する例もあります。
健康維持とオステオパシーの意義
この生理背景を踏まえ、オステオパシー(頭蓋仙骨療法など)では、手技による骨格・筋膜調整子育て脳脊髄液の循環を正常化することを重視します。実際、身体の微細な動きや呼吸と連動して頭蓋骨や仙骨をアプローチすることで、脳が「深呼吸」できる状態を選択し、脳神経細胞の健全な代謝を維持することが可能となるのです。
頭痛や不眠、慢性疲労など自律神経の乱れに悩む方は、脳脊髄液循環の重要性をぜひ意識して、専門的な施術や日々のセルフケア(姿勢・睡眠・呼吸)なども積極的に取り入れてください。